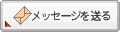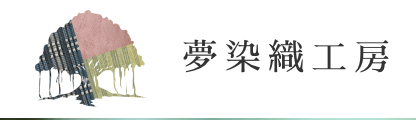
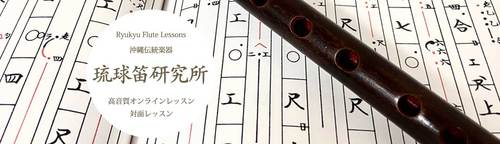
2017年08月16日
浜比嘉島の豊年祭
【浜比嘉島の豊年祭(旧暦6月24日・25日】
昨日、浜比嘉島の豊年祭(初日)に行きました。この年の豊作・豊漁願って2日間続けて行われるもので、女踊りのウスデークの残る地域。
夕方からの豊年祭の流れをザッと覚書き。(覚書ですので個人的な見解が含まれます。参加される場合などは主催者へお問い合わせください)
私が伺ったのは比嘉区。アマミチュー、シルミチューがある方です。
※諸説ありますが、沖縄の祖神とされる女の神、アマミチュー(アマミキヨ)と男の神、シルミチュー(シネリキヨ)が天から久高島に降臨し、津堅島を経て、浜比嘉島に渡りました。水が豊富な浜比嘉島に2つの神が宿り、5人の子どもが生まれました。その子どもたちが、沖縄の人々の祖先になったと伝えられています。
比嘉区には、神の居住地やお墓とされる場所が大切に祀られています。区内には12箇所の拝所や神屋が存在します。
-----以下、覚書------
豊年祭当日の部落内は、車は入れないようになっています。綱が練り歩くので当然です。なので、車で部落内には侵入せず、漁港に停めさせてもらいます。駐車線がある訳ではないですが、綺麗に整列しています。トランプで七並べするように、乱さずに停めます。
夕方5時半ごろに行くと、すでに部落内の道に綱が登場しています。のんびりと(しているように見えます)出発を待ちます。

まずは綱引き
1.綱持って部落内を回る(東と西それぞれの集落を周ります。私が伺ったのは東)
先頭は子どもたちと旗を持った人、次に旗頭、綱に乗った子どもとそれを担ぐ大人たち(男性しかいなかったのですが、決まりなのかは不明)と続きます。
東と西で、出発時間を合わせて練り歩きに出発です。ドラに合わせて「ハーイヤ!」と声をあげて、ぐるっと集落を周ります。

東も西も、白線の引かれた交差点に向かい合って合流。この場所がメイン会場になる。
2.綱引き場で掛け合い
ハーイヤの掛け声で、東と西の綱の上に乗った子どもが向かい合って、競り合う。子どもが太い綱に乗った状態で、わっさわっさと揺らすので、日本昔話のオープニング曲に出てくる「龍の背中に乗った子ども」を思い出しました。

東は女の子、西は男の子が乗っています。半泣きな子もいましたが、よく我慢してました。ちょっとしたジェットコースターより怖いと思う、エライなあ。
3.厄払いの神の舞メーモーイ
子どもが降りた後、中央で滑稽な姿の女性が舞う。カチャーシーに近い感じだけど、闘志パワーが爆発しています。

この女性たちの後ろ姿、奇抜。この滑稽さは厄払いの神なのです。現代は色んなものが手に入るので、個性的に進化してる気がします。始まる前に出会った島の方から「自分が解放されるよ?」という変装のお誘い、コレの事だったのか!とここで気づきました。
4.綱をつないで…
東の綱に西の綱を入れて、棒を刺す。
5.笛の合図で綱を引き合う
ピーっと笛がなると、左右に綱が引かれ、棒がギギっと締まります。
6.勝負が着いたら(今年は西が勝利)…
綱が解かれて、中央で張り合うようにカチャーシーが始まります。先ほどのメーモーイです。こちらは綱を引いてた人も奇抜な厄払いの神たちも混ざって、まさにカチャーシー。ドラや太鼓がガンガンなるので、ちょっとしたトランス。熱冷ましの水も撒かれます。

7.合図で片付けに移る
マイクで終わりが告げられると、さっきまでが嘘のように粛々と解散、片付け、次の準備が行われます。慣れてるなあ。
次のウスデークまでは、時間があるので港に夕陽を見に行ったり、知人のお家でゆくったり。島らしい静かな時間です。でも各家で次の準備していると思うとちょっとワクワクします。

そのうちに太鼓の音が聴こえて、ウスデークの始まり。
ウスデークで回るお家は、それぞれ音響や照明も準備されていました。
1.座開き(というのかは不明ですが)
地謡だけで3曲の演奏
かぎやで風、辺野喜、揚作田

まるで額縁に納まるように地謡と仏壇が、暗闇に浮かんで音が響きます。
続いて、地謡に合わせて3曲の舞踊(舞踊は男性のみ)。
奉納舞踊なのでしょう、仏壇側に向かって踊ります。
かぎやで風

上り口説

揚作田

3.ウスデーク
地謡がはけた(次の家に回る)あと、いよいよウスデークが始まります。
東区が先に舞います。
先ほどの楽器を使った地謡とは、まったく様相が変わります。
小太鼓と年配の女性が唄う歌に合わせて、四つ竹や扇子を持って女性だけが群舞で踊ります。

黄色い紅型の布をかぶって太鼓を持った女性2人と子ども1人が先導して入場します。曲は聞き取りづらかったですが、おそらく3曲ほど。最後は加那ヨー天川の一節だった様に思います。
西区も同じ出で立ちで小太鼓と年配の女性の歌に合わせて踊ります。

両区とも着物は紺地(写真は黒ですが、クンジと言ってたので昔は藍染だったのかもしれません)の絣。帯やハチマキは、東が青、西は白です。足元は島ぞうり(以前は草履ですね)。東は赤、西は黄色でした。
東と西それぞれ違いがあるので、続けて観られるのは、とても贅沢な時間です。
このウスデークが神屋(カミヤー)と呼ばれる家を回って、奉納舞踊をします。
全て回り終えた後、夜遅くから集落の中央に組まれた舞台で余興が始まります。
これは初日(旧暦6月24日)の様子です。2日目(旧暦6月25日)の今日は舞台余興が早い時間から始まるそうです。
豊年祭は準備期間から終わって打ち上げまでが一連の「祭り」です。一部だけ拝見しただけでは分からない島が、そこにはあるはずですね。素敵な豊年祭です。
昨日、浜比嘉島の豊年祭(初日)に行きました。この年の豊作・豊漁願って2日間続けて行われるもので、女踊りのウスデークの残る地域。
夕方からの豊年祭の流れをザッと覚書き。(覚書ですので個人的な見解が含まれます。参加される場合などは主催者へお問い合わせください)
私が伺ったのは比嘉区。アマミチュー、シルミチューがある方です。
※諸説ありますが、沖縄の祖神とされる女の神、アマミチュー(アマミキヨ)と男の神、シルミチュー(シネリキヨ)が天から久高島に降臨し、津堅島を経て、浜比嘉島に渡りました。水が豊富な浜比嘉島に2つの神が宿り、5人の子どもが生まれました。その子どもたちが、沖縄の人々の祖先になったと伝えられています。
比嘉区には、神の居住地やお墓とされる場所が大切に祀られています。区内には12箇所の拝所や神屋が存在します。
-----以下、覚書------
豊年祭当日の部落内は、車は入れないようになっています。綱が練り歩くので当然です。なので、車で部落内には侵入せず、漁港に停めさせてもらいます。駐車線がある訳ではないですが、綺麗に整列しています。トランプで七並べするように、乱さずに停めます。
夕方5時半ごろに行くと、すでに部落内の道に綱が登場しています。のんびりと(しているように見えます)出発を待ちます。

まずは綱引き
1.綱持って部落内を回る(東と西それぞれの集落を周ります。私が伺ったのは東)
先頭は子どもたちと旗を持った人、次に旗頭、綱に乗った子どもとそれを担ぐ大人たち(男性しかいなかったのですが、決まりなのかは不明)と続きます。
東と西で、出発時間を合わせて練り歩きに出発です。ドラに合わせて「ハーイヤ!」と声をあげて、ぐるっと集落を周ります。

東も西も、白線の引かれた交差点に向かい合って合流。この場所がメイン会場になる。
2.綱引き場で掛け合い
ハーイヤの掛け声で、東と西の綱の上に乗った子どもが向かい合って、競り合う。子どもが太い綱に乗った状態で、わっさわっさと揺らすので、日本昔話のオープニング曲に出てくる「龍の背中に乗った子ども」を思い出しました。

東は女の子、西は男の子が乗っています。半泣きな子もいましたが、よく我慢してました。ちょっとしたジェットコースターより怖いと思う、エライなあ。
3.厄払いの神の舞メーモーイ
子どもが降りた後、中央で滑稽な姿の女性が舞う。カチャーシーに近い感じだけど、闘志パワーが爆発しています。

この女性たちの後ろ姿、奇抜。この滑稽さは厄払いの神なのです。現代は色んなものが手に入るので、個性的に進化してる気がします。始まる前に出会った島の方から「自分が解放されるよ?」という変装のお誘い、コレの事だったのか!とここで気づきました。
4.綱をつないで…
東の綱に西の綱を入れて、棒を刺す。
5.笛の合図で綱を引き合う
ピーっと笛がなると、左右に綱が引かれ、棒がギギっと締まります。
6.勝負が着いたら(今年は西が勝利)…
綱が解かれて、中央で張り合うようにカチャーシーが始まります。先ほどのメーモーイです。こちらは綱を引いてた人も奇抜な厄払いの神たちも混ざって、まさにカチャーシー。ドラや太鼓がガンガンなるので、ちょっとしたトランス。熱冷ましの水も撒かれます。

7.合図で片付けに移る
マイクで終わりが告げられると、さっきまでが嘘のように粛々と解散、片付け、次の準備が行われます。慣れてるなあ。
次のウスデークまでは、時間があるので港に夕陽を見に行ったり、知人のお家でゆくったり。島らしい静かな時間です。でも各家で次の準備していると思うとちょっとワクワクします。

そのうちに太鼓の音が聴こえて、ウスデークの始まり。
ウスデークで回るお家は、それぞれ音響や照明も準備されていました。
1.座開き(というのかは不明ですが)
地謡だけで3曲の演奏
かぎやで風、辺野喜、揚作田

まるで額縁に納まるように地謡と仏壇が、暗闇に浮かんで音が響きます。
続いて、地謡に合わせて3曲の舞踊(舞踊は男性のみ)。
奉納舞踊なのでしょう、仏壇側に向かって踊ります。
かぎやで風

上り口説

揚作田

3.ウスデーク
地謡がはけた(次の家に回る)あと、いよいよウスデークが始まります。
東区が先に舞います。
先ほどの楽器を使った地謡とは、まったく様相が変わります。
小太鼓と年配の女性が唄う歌に合わせて、四つ竹や扇子を持って女性だけが群舞で踊ります。

黄色い紅型の布をかぶって太鼓を持った女性2人と子ども1人が先導して入場します。曲は聞き取りづらかったですが、おそらく3曲ほど。最後は加那ヨー天川の一節だった様に思います。
西区も同じ出で立ちで小太鼓と年配の女性の歌に合わせて踊ります。

両区とも着物は紺地(写真は黒ですが、クンジと言ってたので昔は藍染だったのかもしれません)の絣。帯やハチマキは、東が青、西は白です。足元は島ぞうり(以前は草履ですね)。東は赤、西は黄色でした。
東と西それぞれ違いがあるので、続けて観られるのは、とても贅沢な時間です。
このウスデークが神屋(カミヤー)と呼ばれる家を回って、奉納舞踊をします。
全て回り終えた後、夜遅くから集落の中央に組まれた舞台で余興が始まります。
これは初日(旧暦6月24日)の様子です。2日目(旧暦6月25日)の今日は舞台余興が早い時間から始まるそうです。
豊年祭は準備期間から終わって打ち上げまでが一連の「祭り」です。一部だけ拝見しただけでは分からない島が、そこにはあるはずですね。素敵な豊年祭です。
Posted by 夢布 at 12:16│Comments(0)
│ふらり。